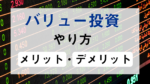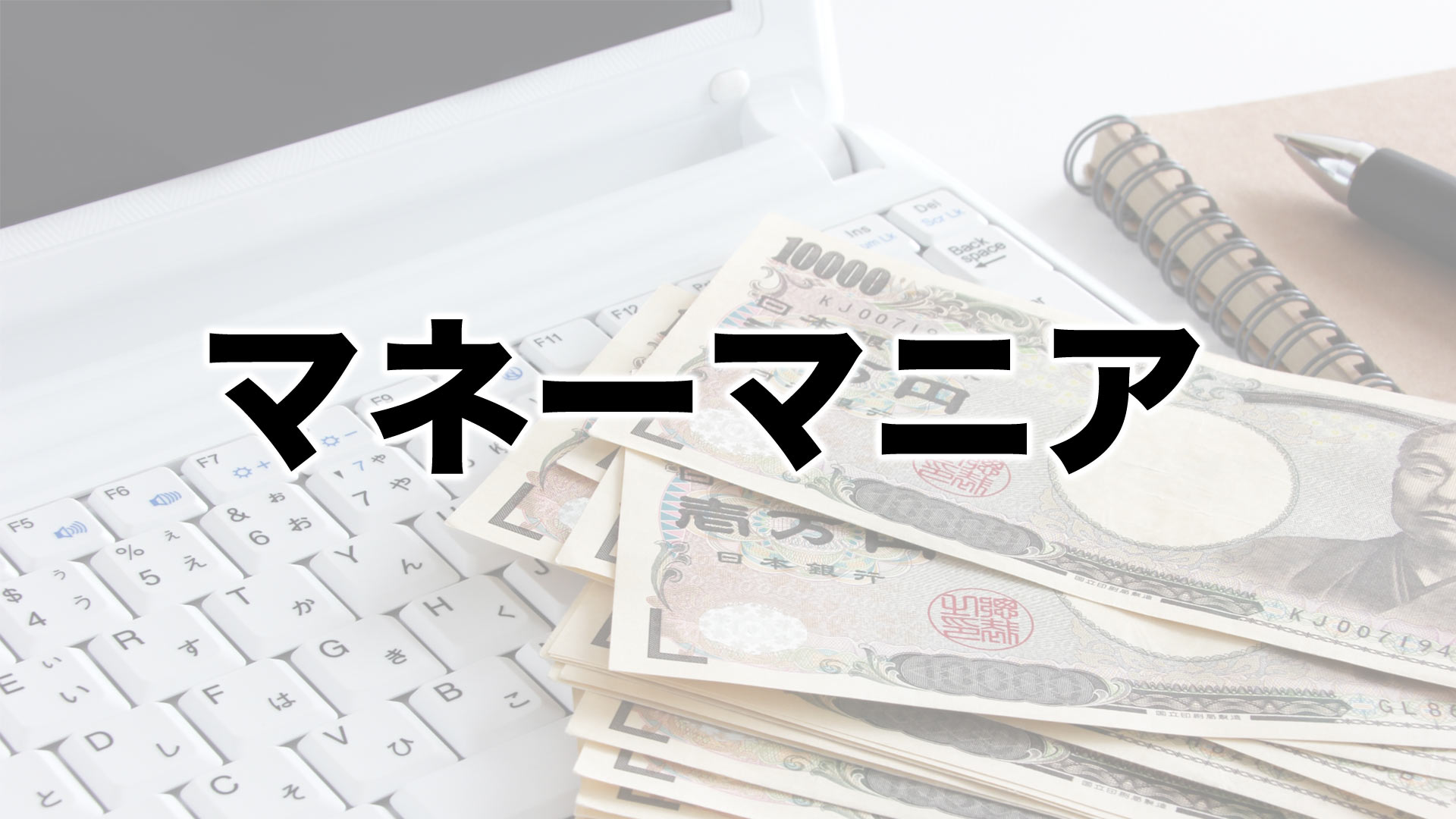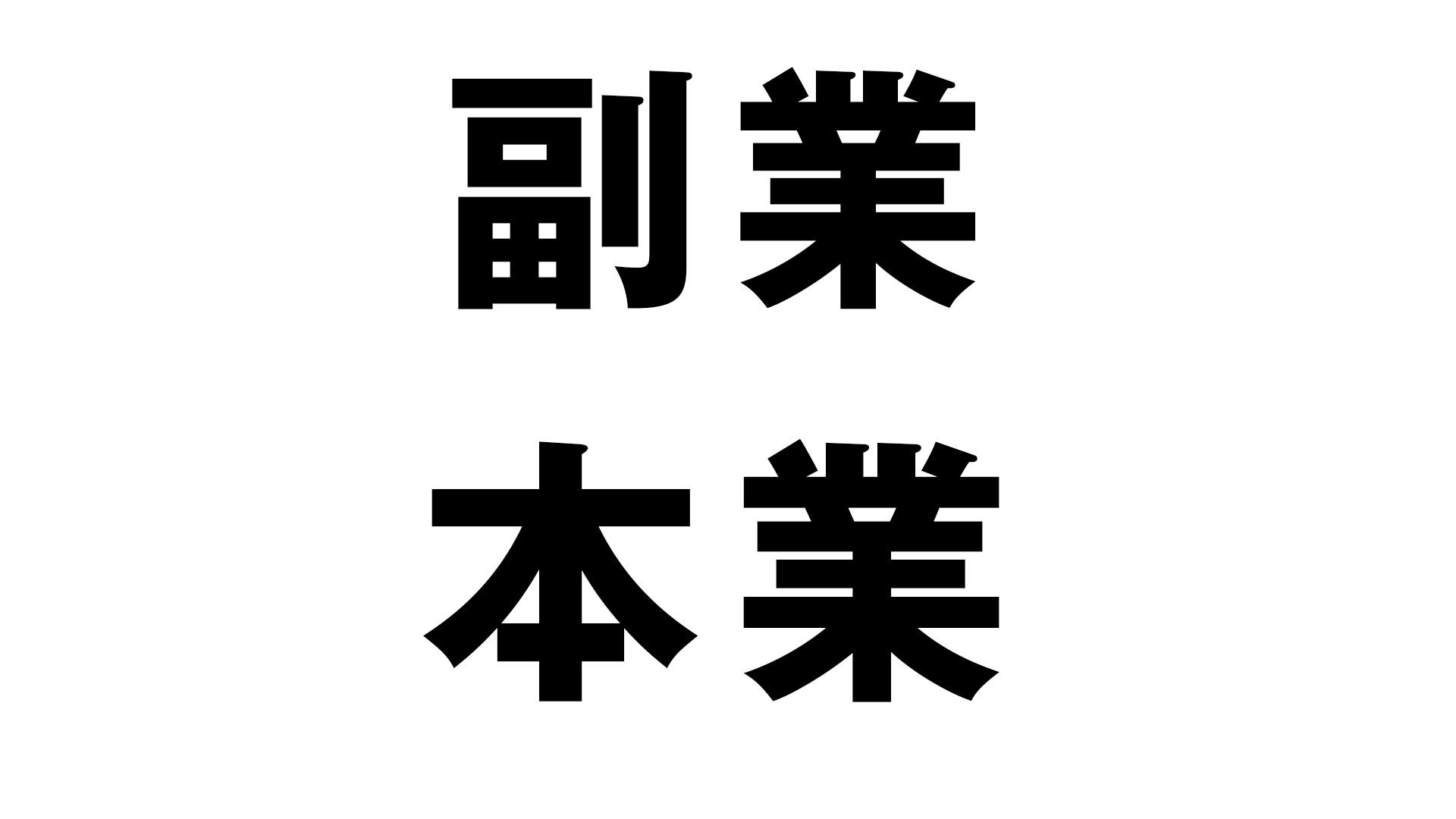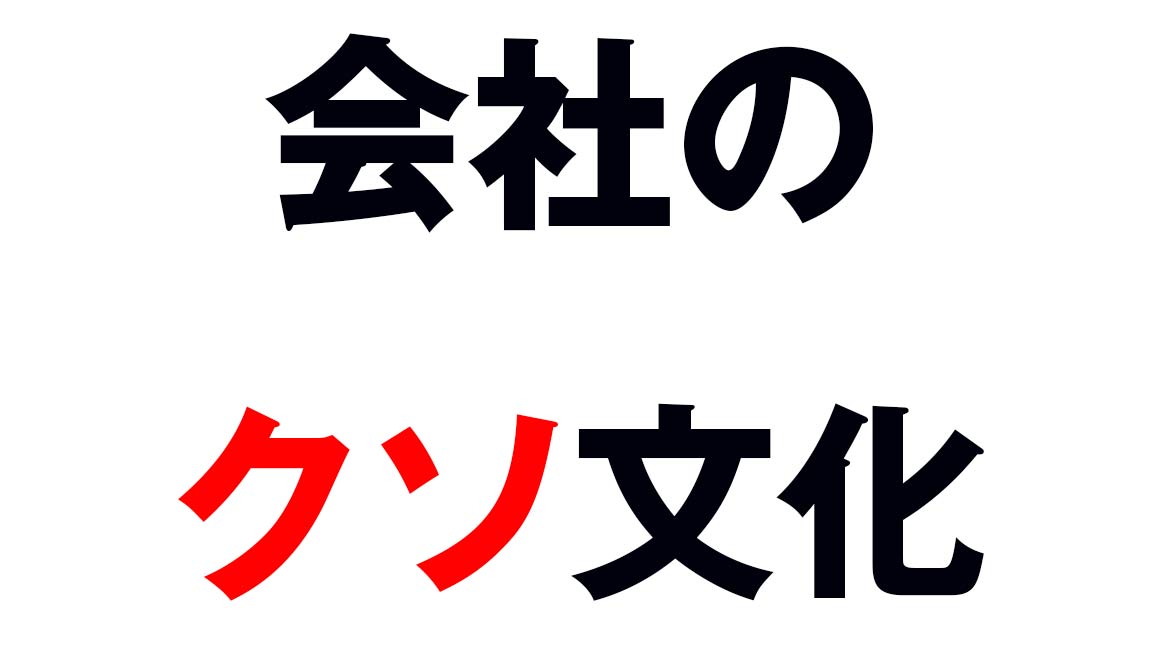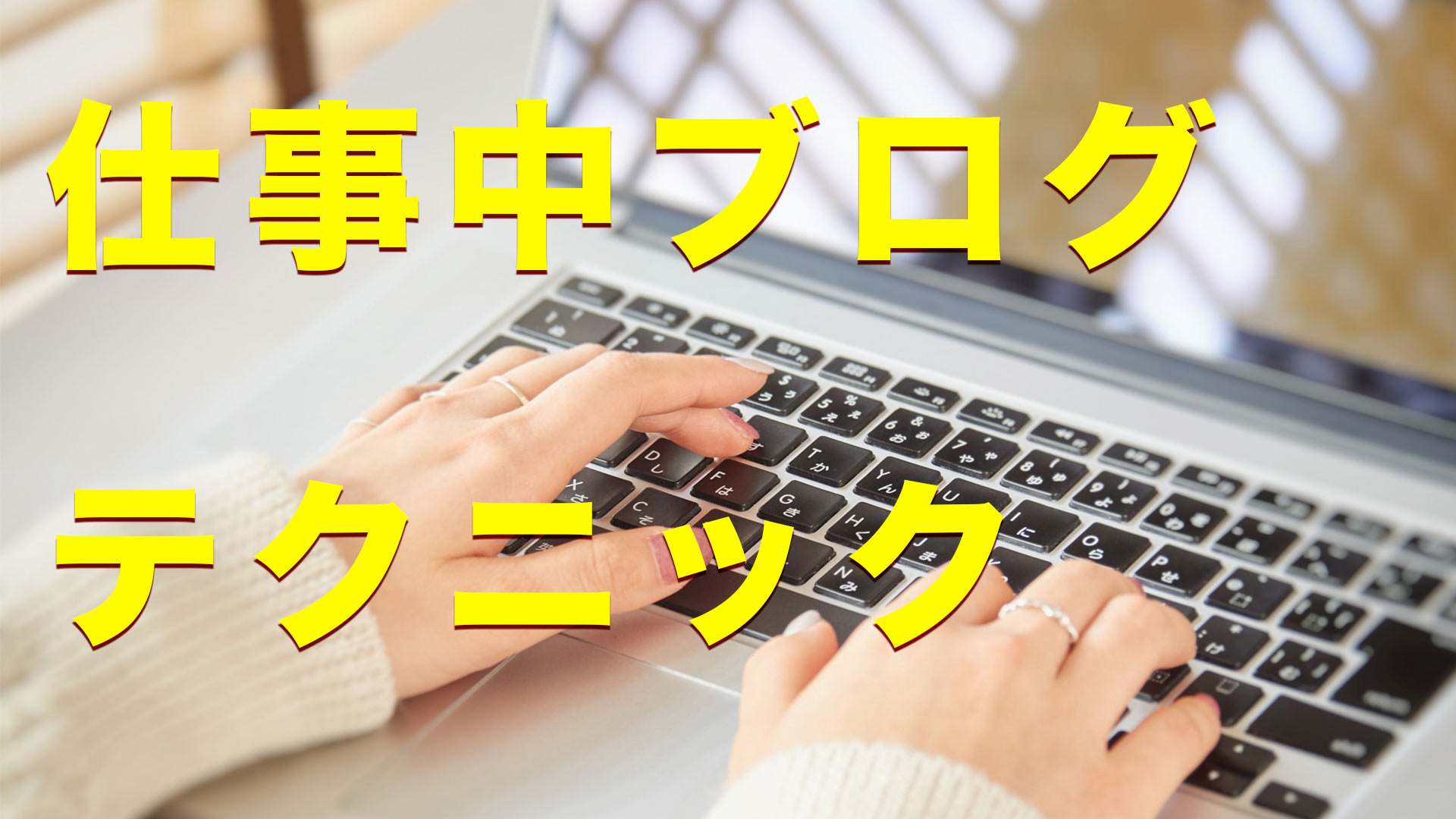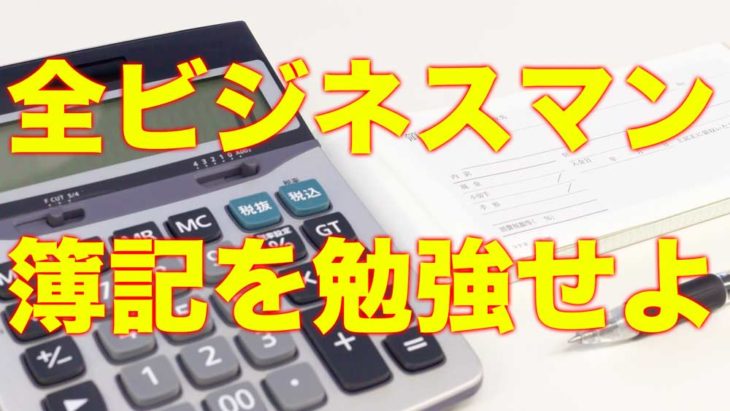
資格マニア と揶揄されることもある僕ですが、数ある取得資格の中でも最も「勉強してよかった」と思えるのが簿記です。
簿記と言うと、なんか古くさい印象であったり、時代遅れのイメージが拭えないかもしれません。
ですが、簿記は非常に優秀なシステムであり、誰でもやっておいて損はない分野です。
今回は全ビジネスマンが簿記を学ぶべき理由について書いていきたいと思います。
目次
どんな人におすすめなのか
まず、全ビジネスマンとはいうものの、具体的にどんな人が簿記を学ぶべきなのでしょうか。
- 管理職のサラリーマン。または将来管理職を目指すサラリーマン
- 起業を考える脱サラ志向サラリーマン
- 中小企業の社長・オーナー
などにおすすめしたいです。
まぁ、一兵卒社員を除いてほぼすべてのビジネスマンが該当します。
なぜ簿記をおすすめするのか

僕が簿記をおすすめするのは、主に
- 社内の資料の理解が深まる
- お金の動きがつかめるようになる
- 現在の会社の財務状況が分かるようになる
- 管理会計・原価計算の仕組みが分かる
このあたりですね。
一つずつ見てみましょう。
社内の資料の理解が深まる
特に管理職になってくると、売上や粗利、在庫、経費などの勘定科目でもって管理する資料を目にすることが多くなります。
それらの資料の科目名は「売上」や「給料」など、一見でどういう内容か分かるものも多いですが、「減価償却費」とか「建物」とかいう科目についてはいまいち理解し辛い科目もあります。
簿記を学習すると、減価償却費の計算方法であったり、建物や車両などの資産項目がいずれ費用として配分されていくというイメージが出来るようになります。
減価償却費は売上や粗利が多い少ないに関わらず毎期一定額が計上されるわけですので、圧縮ができない費用ということになります。
すると、社内資料を見たときでも、営業利益が悪化している場合に「減価償却費ってのを減らせば良いんじゃね?」みたいなトンチンカンな発想もしなくなるでしょう。
お金の動きがつかめるようになる
自分が勤める会社の資金がどのように使われ、どのような資産に変化しているのかを簿記の結晶とも言える「貸借対照表」で見ることができます。
現金や預金がいくらあるか、得意先への売掛金や受け取った手形はどれだけあるのか。
逆に借金や、仕入先への買掛金はどれだけあるのか。
銀行からいくら位借金しているのか。
等は、貸借対照表を見れば一発で理解できますが、簿記を勉強していないと正直どう見ていいかがわからないと思います。
自分が勤める会社ですから、状況をしっかり把握しておきたいですよね。
ただし、会社によっては貸借対照表とか損益計算書は社内に公表しない場合も多いです。
現在の会社の財務状況が分かる
これも前項と同じですが、会社の財産(資産)や借金などの財務状況を理解することで、会社の財務健全性を見ることができます。
繰越利益剰余金 など、一見して意味がわからない概念の科目をみれば、「あぁまだ繰越利益剰余金が売上の数年分あるからうちの会社は余裕あるな」とか「繰越利益剰余金がマイナスになっている。これは債務超過の会社ではないのか?逃げろー!!」等の財務分析が出来るようになります。
管理会計・原価計算の仕組みが分かる
これは、簿記2級(日本商工会議所主催の簿記2級です)で学習する分野ですが、特に製造業や建設業の場合の「原価計算」の仕組みを学習することになります。
実は、製造業とかだけでなく、この原価計算の仕組みは日常生活でも非常に役に立ちます。
詳しくは触れませんが、僕はこの分野だけでも「簿記をやってよかった」と思えました。
簿記2級の知識があれば、出世したときに絶対に役立つ

簿記を学習するメリットを紹介しましたが、簿記の学習といってもどこまでをやれば良いのでしょうか。
簿記の試験は、いろいろな団体がそれぞれ異なる検定を行っています。
その中でも最もメジャーなのが、日本商工会議所が主催するいわゆる「日商簿記」という簿記検定です。
日本で「簿記◯級持ってる」という話のときは、殆どが前提としてこの日商簿記のことを言います。
3級は個人事業レベル、2級は中小企業レベル、1級は上場企業や大企業レベル
の内容だとざっくりと理解すれば良いでしょう。
正直1級は、かなり難易度も高いですし、ビジネスでその知識を活かす場はほとんどありません。
よほどの会計好きか資格マニアか、税理士や公認会計士を目指す人がその受験資格のために受ける検定というイメージです。
大企業であっても、2級で十分です。
2級を取得できれば、管理職として必要な会計知識はほぼ網羅されているでしょう。
会社経営者は100%簿記を勉強すべし
会社経営をしている人でも「オレ数字弱いから経理部長に全部任せてある」という人もいますが、これは最悪です。
数字に弱い人が経営をやっても、意思決定の元になる根拠は「自信、勢い、勘」となることがほとんどでしょう。
しっかり自社の財務状況を把握して、どこまでの新規事業や設備投資が出来、何年で回収出来るのか、という計数管理ができて初めて会社の意思決定がなされるべきです。
もちろん、その意思決定のための基礎数値を経理担当に出させる事は問題はありませんが、一番キモになる部分の判断を経理担当にまかせてはいけません。
正しい意思決定を行うためには、出された資料の数値の意味合いをしっかり読み取り、リスクを把握する数字力が必要です。
そんために簿記を学習することは、決して無駄にならないはずです。
簿記2級は独学で取れる

話は戻り、簿記2級をおすすめする理由の一つに、「独学でも取れる」ということがあります。
実際、僕は簿記の勉強を独学ではじめて2ヶ月後に簿記3級を98点、6ヶ月後に2級を96点で合格しています。
最近、少し簿記2級の試験制度が改定になり難しくなったと言われますが、それでも15~30%位の合格率があります。
商業高校の学生などが記念受験などで受けるのも多いので、まともに勉強をする人の合格率は50%を余裕で上回っているというのが実感です。
専門学校では二級の口座が7-8万円する場合もありますので、なかなか手が出しづらいと思いますので是非まずは独学で簿記3級を目指してみてください。
その後、興味が持てるようならそのまま独学で2級まで取得することは十分可能です。
まとめ
以上、ビジネスマンが簿記を学習すべき理由と、具体的に簿記2級をめざすべき理由を説明してきました。
就職活動をする場合でも、簿記の資格を持っていれば経済感を持っているビジネスマンだという認識を採用側が持ってくれますので、かなりのアドバンテージになるかと思います。
時間やテキスト代に多少のコストはかかりますが、投資に対するリターンの率は非常によく、効率的な学習分野ですので、是非勉強をしてみてくださいね。